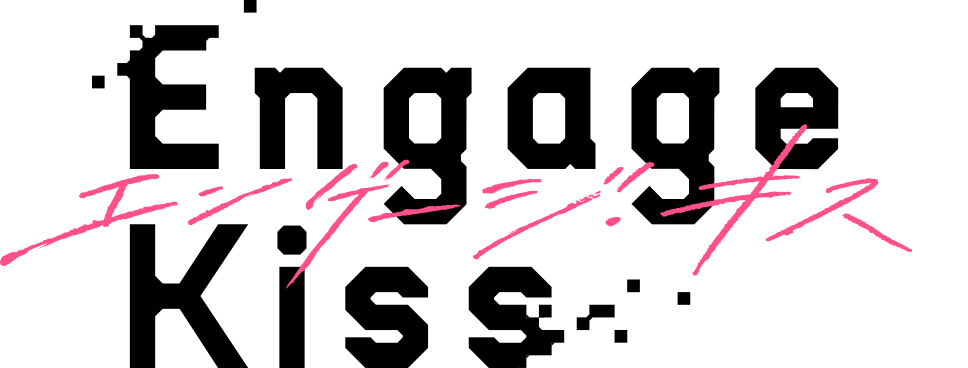Special
オフィシャルインタビュー第4弾
田中智也(監督)×藤田祥雄(アニメーションプロデューサー)
――A-1 Picturesの藤田さんといえば、「Fate/Apocrypha」を筆頭にバトルもの、アクションものに強いアニメーションプロデューサーという印象です。なので、丸戸史明さんがシナリオを手掛ける美少女ラブコメを手掛けると聞いたときは驚きました。確認になりますが、これまで美少女ヒロインがメインの作品を手掛けたことは?
藤田 まったくありませんでした。だから弊社の柏田(真一郎)から企画の話が来たときは、「本当に俺でいいの?」と思いましたね(笑)。それぐらい自分にとっては異次元の題材でした、ラブコメって。
田中 自分も藤田さんから監督の依頼があったとき、「なぜこの人からラブコメの企画を打診されるんだろう?」と思いましたからね。何かの間違いじゃないかと(笑)。
藤田 ですよね。しかもそうおっしゃる田中さんも、ラブコメ作品ってこれまでやっていなかったですよね?
田中 そうなんです。自分がこれまで関わってきたのは、もともと好きだったこともあって、ほぼ少年マンガ原作ものです。あとはちょこちょこスポーツものをやっていたくらい。ラブコメもののアニメも見てはいましたけど、仕事で関わったことがなかった。だからこの作品の監督を引き受けたのは、挑戦の気持ちが大きかったです。
――藤田さんが田中監督にこの作品をおまかせしたいと考えたのは、なぜだったんですか?
藤田 田中さんが弊社で『七つの大罪 戒めの復活』の副監督のお仕事をされているとき、本当に少しなんですけれども、自分も制作進行という形で参加させていただいたんです。そこでいろいろとやりとりをさせていただいたときの、素材のチェックのやり方であったり、現場の空気感の作り方を拝見していて、非常に力量のある方だと感じていたんです。それに、自分の感触だけじゃなく、まわりの方からもとてもいい評価が噂として聞こえてきて。
田中 そうなんですか(笑)。
藤田 ご本人がいらっしゃる前でそんな話をするのも恐縮ですが、でも、事実です。で、そうした点を踏まえて、自分が弊社の自社企画、それも原作のない、オリジナルアニメの企画を投げられたとき、どういう方に監督をしていただきたいかと考えたら、最初にぱっと浮かんだのが田中さんだった。オリジナルってやっぱり、難しいんですよね。原作ものと違って、作品づくりの明確な指針がない。だから現場で、強いリーダーシップを取る人が必要になる。そういう資質があり、また、ラブコメに不慣れな自分と、一緒になって挑戦してくれるような人って誰だろう? いわゆるバディ(相棒)みたいな形で、この作品でともに戦っていける人は誰だろう? と考えたら、田中さんしか思いつかなかった。
――実際に作品の打ち合わせを始めてみて、いかがでしたか? 不慣れなジャンルで、戸惑われました?
田中 シュウに関しては、こちらからいろいろ丸戸さんに「クズ」っぷりについて提案したんですけど、ほとんどのアイデアが「クズすぎる」と却下されました(笑)。
――ノリノリじゃないですか(笑)。最初のお話しから考えると、これまたちょっと意外です。
藤田 丸戸さん、ああ見えて……というのも大変失礼ですが(笑)、とても真面目な方なんですよ。ちゃんと放送コードのこととかも考えてくださる。で、僕たちは、意外とそういうことを気にせず、「リアルなクズってこんな感じじゃない?」みたいなアイデアを出してしまっていたんです。でも考えてみれば、それは多分、他人から嫌われるクズなんですよね。
田中 一部のアイディアに関しては、うまく言葉を柔らかくして取り入れてくださって、ありがたかったですね。
――例えばどんなところですか?
田中 シュウがアヤノと付き合ってたときに、アヤノのお金で浮気したとか……もちろん実体験じゃないですよ!? 学生時代の悪友とか、そういう、まわりで見聞きしてきた人の話をモデルにアイディアを出しました。あと、僕も藤田さんも決して悪ノリしていただけではなくて、アニメでクズを描くときは、やっぱり現実のクズよりもさらに激しいクズとして描かないと、なかなか生々しいクズだと感じてもらえないかなと思ったので、結構過激なネタだしをしていたんです。
藤田 おっしゃる通り。……ただまあ、とはいえ、どちらかというと田中さんや僕の方が、丸戸さんや柏田よりもクズをストイックに捉えすぎていたのかもしれません(笑)。でも、僕たちがクズなのではなくて、あくまでクズなアイディアを出していただけです。ホントです!
田中 ……ともあれ、そうやって出したネタを、丸戸さんやつなこさんが、「クズではあるけど、キャラクターを愛して欲しい」という気持ちで、柔らかくバランスを調整してキャラクターに盛り込んで下さったんです。
藤田 そのあたりはやっぱり、みなさんの手腕はさすがだなと感じましたね。
――そんなお話をうかがうと、挑戦するつもりで美少女ラブコメに参加してみたら、実はむしろ企画と相性が良かったようにお見受けします。
藤田 そうですね。あとまあ、美少女ラブコメではあるんですけど、ベタな路線じゃなかったというか。ちょっとひねった部分があったから、逆にアクション畑や少年マンガ畑でやってきた、純粋なラブコメ畑の人間ではなかった自分たちが入り込みやすかったのかな? とも思います。
――キャラクターデザインをはじめ、スタッフィングはどのような狙いで固められたのでしょうか。
藤田 キャラクターデザインと総作画監督をお願いした滝山真哲さんは、キュートで、どこか色気のある絵を描かれる方なんです。かわいいけど、ただかわいいだけじゃないぞ、みたいな。つなこさんの絵は、僕の印象では非常にピュアなものだったので、そうしたピュアさと色気を兼ね備えた絵を描くデザイナーをマッチングさせることで、丸戸さんの求めるフェチな部分にアプローチできないかなと考えました。画風の近い方同士を合わせるわけではない、少し実験的なことをやりましたね。サブキャラクターデザイン・総作画監督の古住千秋さんは、とにかく地のスペックが高い。キャラクターデザインのポイントを的確に見抜いて、非常に正しくご自分の絵に落とし込んでくれる方なんです。僕はこういう力のある方のことを、いつも「目がいい」と表現しているんですけど、古住さんは非常に「目がいい」方の印象があります。
田中 作画まわりは、個々の原画さんもがんばってくれていますね。特にアクションを描いてくれている方のがんばりには頭が下がります。実は絵コンテでは、あんな大変なことにはなってないものも多いんです。
――アクション設計の菅野芳弘さん、アクション作画監督の丸山大勝さんが専任で立たれていることで、アクションはもともとの各話の絵コンテからさらにパワーアップを?
田中 それにくわえて、さらに原画さんがそれぞれ良くしよう、良くしよう……と力を入れてくれるんです。
藤田 アクションものってやればやるだけというか、いいものにしようとをすればするほど、すごさがインフレしていくわけですよね。どこかで止めないとな……とアニメーションプロデューサーとしては思いながらも、どんどん盛り上がってしまいました(苦笑)。ありがたいことなんですけどね。アニメーター全体でいえば、演出もやりながら原画の作業もしてくれている森公太くん。それから永野裕大くんに、田中大喜くん。丹羽 巧くんは回を増すごとに絵が良くなってきていますね。あとはアクション関係で、加藤滉介くんの仕事は非常に目を見張るものがありますね。アクションシーンは超高密度な絵をずっと動かすことはできないというか、動かすためにあえて崩す部分があるんですけど、加藤くんは密度の高さと崩し方の塩梅が非常にうまいんです。キャラの魅力を損なわずに、激しく動かしてくれる。これは描き手として相当な技量がないとできないことです。
――スゴい方が揃われているんですね。作画まわり以外で、特に気を配ったスタッフィングはありますか?
藤田 それでいうと今回、編集・色彩設計・音響監督は田中監督からのご要望で決めましたよね。
田中 そうですね。編集に関しては、この作品は会話のテンポ感がすごく大事な作品になると思ったので、本当に細かくカットしてくれる方と組みたかったんです。編集の坂本久美子さんとは、『おそ松さん』に各話スタッフで参加したときに一緒にやらせていただいて、そのときの印象が素晴らしかったんです。『おそ松さん』は1カットの中で5、6ヶ所ぐらいコマを抜くことがあるくらい、ものすごく編集への要求がシビアな作品で、でもそれをやることでテンポが抜群に良くなっていたんです。そのくらいのテンポ感を、丸戸さんの書く会話劇では出したいなということで、お願いさせていただきました。
藤田 僕は今回初めて組ませていただいたんですけど、本当に、めちゃめちゃ腕の立つ方ですね。「こういう切り方もできるんだな」とか、「この絵とこの絵でも全然繋いで見られるな」とか、編集作業で驚かされる瞬間がたくさんあります。監督がこの作品が始まる前におっしゃったことの意味を、今、現場で痛感していますね。
――色彩設計の岡崎菜々子さんと、音響監督の高寺たけしさんはどのような理由で?
田中 岡崎さんは『七つの大罪 戒めの復活』で色彩設計をやってくださっていて、そのときにキャラクターを大事にされる方だという印象を受けたんです。今回、やはりキャラ推しの作品だということで、キャラクターの魅力をより伝えるためにお願いしました。高寺さんは以前、別の作品でご一緒させていただいたとき、本当に優しくて、現場の空気感を大事にされている姿が印象に残っていたんです。監督だけじゃなく、各話の演出さんの意見を始め、その場のみんなの意見を大事にされながら、うまくバランスを取ってお仕事をされていたんですよね。そうした空気感がこの作品にも必要だと感じていたので、ぜひお願いしたいと。
――ここまでお話しいただいた点以外で、監督が映像面でこだわったポイントはありますか?
田中 背景美術でなるべくイメ背(イメージ背景)を使わず、リアルなものを使うとかもあるんですけど……もっともこだわったのは、やはりシュウとキサラのキスシーンですかね。タイトルに「Kiss」と入っていることもあり、そこは何よりも気合を入れようと思って、関わるスタッフさんたちにも意気込みを伝えましたし、自分としてもあれこれアニメを見て、キスシーンを研究してやってみました。「こんなキスやっていいのかな?」っていうぐらい、1話から攻めたものをやりましたね(笑)。
藤田 がんばっていただきましたよね。唾液が糸引いてますからね……。
田中 しかも、そこからどんどんパワーアップして……。
藤田 回を重ねるごとにドラマも深くなってくるので、キスシーンもどんどん盛られていきますよね。ちょっとだけ、作っている自分たちも見るのが恥ずかしいくらいで……視聴者のみなさん、先の話数もご期待ください(笑)。
田中 ですね。ただその、キスシーンのこだわりも見てはもらいたいですが、そこにつながっている、シュウとキサラの関係性の部分にも注目していただきたいですね。普通のアニメみたいに、ふたりとも人間的に成長することはないんですけど(笑)、関係性が回を追うごとに変わっていって、最後どうなるのか。全体としてはそこが見どころだと思います。
――監督、ラブコメもですけど、ヤンデレヒロインを描くのも初挑戦ですか?
田中 そうですね。そこも挑戦です。
――健やかな少年の成長を描かれてきた方が、そんな新境地にも……。
藤田 不健全な大人たちの映像をお願いしてしまって、本当にすみません! なんだか今日の取材で、ふつふつとそんな気持ちが湧いてきてしまいましたよ……。
田中 いやいや(笑)。
――藤田さんは、あらためて今作のみどころを語るとするなら?
藤田 僕は……田中さんとちょっと違う角度からお答えすると、感覚が麻痺しているのかもしれないですけど、シュウとキサラとの関係にせよ、アヤノ、シャロンとの関係にせよ、丸戸さんが描かれている人間関係って、総じて「純愛」だなと思い始めてるんですね。すごいピュアだなあと。特にシリーズ後半の話数では、それを強く感じる瞬間が出てくるんです。本当に丸戸さんはエンターテイナーだなと、シナリオ打ち合わせでそのあたりの展開を読んだときに思ったんですよ。ぜひご覧いただいている皆さんにもそういう、丸戸さんならではの、とてもキュートで、ユニークな「純愛」を体感してほしいです。
――とても素敵なお話なんですけど、監督が横で、なんともいえないいい笑顔をされておられる……?
田中 いやいやいや!(笑) 藤田さんのおっしゃること、めっちゃわかりますよ。わかるんですけど……。
藤田 一応前置きしましたからね? 「感覚が麻痺しているのかもしれない」って(笑)。
田中 うん、そうだね……「純愛」……「行き過ぎた純愛」「歪んだ純愛」みたいな……。
藤田 行き過ぎたところ、歪んだところも含めて、よくよく考えるとピュア……みたいな? そんな「純愛」が、きっと感じられるはずです。たぶん。きっと。信じるか、信じないかは……あなた次第! ……ということで、どうでしょうか(笑)。